積立NISAで含み損に悩んでいる方へ、元本割れを目の当たりにすると将来が不安になりますよね。
特に「積立NISAの元本割れが借金になるのでは?」と検索して不安を抱えている人は多いはずです。
この記事では返済義務の有無や証券会社からの請求の可能性、追証や税務上の扱いなどを分かりやすく解説します。
原因や具体的な対処法、リスクを抑える運用戦略まで押さえて、冷静に判断できるポイントをお伝えしますのでぜひ続きをご覧ください。
積立NISAの元本割れは借金になるのか

積立NISAで投資元本を下回る評価損が出ても基本的に借金にはなりません。
投資信託の商品価値が下がることと債務を負うことは性質が異なります。
以下で返済義務や証券会社からの請求の有無などを順に説明します。
返済義務の有無
積立NISAで保有する投資信託が元本割れしても投資家に返済義務は発生しません。
評価損は保有する資産の時価が下がっている状態を示すだけです。
資産を売却しなければ損益は確定しない点も押さえておくと良いです。
証券会社からの請求
通常の積立NISA口座で評価損に対して証券会社から金銭の請求が来ることはありません。
証券会社が請求を行うのは貸株や信用取引など別の取引で担保不足が生じた場合です。
| 状況 | 結果 |
|---|---|
| 積立NISAでの評価損 | 請求は発生しない |
| 信用取引での損失 | 追証の可能性あり |
| 貸株などの特殊取引 | 個別の契約による対応 |
追証との関係
追証は保証金や担保の不足を補填するために投資家に追加の入金を求める制度です。
積立NISAは現物投資であり担保を使った信用取引ではないため追証の対象にはなりません。
- 追証は信用取引の制度
- 積立NISAは現物買付
- 追証が発生するのは担保不足の場合
したがって積立NISAの元本割れで追加請求が来ることはありません。
信用取引との違い
信用取引は借入や担保を使って取引を行うため損失が拡大すると債務が発生する可能性があります。
一方で積立NISAは自分の資金で投資信託を買う仕組みであり借金をしている状態ではありません。
信用取引では追証や強制決済による損失確定がある点を理解しておくと安心です。
投資信託の償還タイミング
投資信託は基準価額が下がっていても保有を続けることで回復を待つことができます。
ただし運用実績や市場環境によっては元本割れが長期化することもあります。
売却するタイミングは個人のリスク許容度や資金計画に応じて判断してください。
税務上の損失扱い
積立NISA口座内での評価損は非課税枠内で管理されるため損益通算や繰越控除の対象にはなりません。
課税口座での投資損失と扱いが異なる点に注意が必要です。
税務上の取り扱いについて不明点があれば税理士や証券会社に相談することをおすすめします。
積立NISAの元本割れが起きる仕組み

積立NISAで元本割れが起きるとは買った投資信託などの評価額が購入時より下がることを指します。
価格は常に変動するため評価額が一時的に下回ることはあり得ます。
元本割れの発生自体は借金になるわけではありませんが借入金で投資している場合は返済負担が残る点に注意が必要です。
市場価格の変動
株式や債券を内包する投資信託は市場の需給や企業業績金利動向で価格が上下します。
景気悪化や業績下方修正は基準価額を押し下げる要因になります。
積立投資は価格が下がったタイミングで多く買えるため長期で平均取得単価を下げる効果があります。
一方で短期的に売却すると元本割れが確定して損失になる点は理解しておく必要があります。
為替リスク
海外資産に投資するファンドは為替変動が基準価額に影響します。
円高が進むと外貨建て資産の円換算価値が下がり元本割れを招くことがあります。
為替ヘッジの有無でリスクの度合いは変わります。
為替リスクを避けたい場合は国内資産中心のファンドを選ぶかヘッジありの設定を確認してください。
運用コストの影響
投資信託には信託報酬や売買手数料などのコストが存在します。
長期間にわたりコストが積み重なるとトータルのリターンに差が出ます。
| コスト項目 | 影響の内容 |
|---|---|
| 信託報酬 | 継続的な負担がリターンを削る |
| 売買手数料 | 取得時売却時のコスト増加 |
| 隠れコスト | トータルコストの上振れ要因 |
分配金と基準価額の関係
分配金を出すタイプのファンドは分配時に基準価額が下がる性質があります。
分配金が再投資されない場合は手元に現金が戻る一方で基準価額はその分減少します。
積立NISAでは再投資型のファンドを選ぶことで基準価額の変動が直接的に手取りに影響しにくくなります。
分配金があることで短期的に元本割れのように見えるケースもあるため仕組みを知っておくことが大切です。
短期保有の影響
積立NISAは長期投資を前提とした制度であるため短期保有だと価格変動の影響を受けやすいです。
短期での売買を繰り返すとコスト負担やタイミングリスクで損失が出やすくなります。
- 一時的な評価額の下落で損失確定
- 購入直後の価格変動で不利になる可能性
- コストが相対的に重くなる
積立NISAで元本割れでも借金が発生しない具体的根拠

積立NISAは投資元本が目減りしても投資家に借金が生じない仕組みになっています。
その背景には有限責任の原則やNISA口座の取扱い、証券取引に関するルールがあります。
有限責任の原則
有限責任とは投資家が出資した範囲でのみ損失を負うという原則です。
個人が積立NISAで購入した投資信託やETFの価値が下がっても、投資家が追加で支払う義務は基本的に発生しません。
これは会社の負債や信用取引のように借入を伴う取引とは性質が異なります。
有限責任の考え方は投資の基本ルールとして法律や金融商品取引の実務に反映されています。
NISA口座の仕組み
NISA口座は非課税枠を設けた個人用の投資口座であり課税の扱いが特別です。
積立NISAでは原則として現金での買付が行われるため信用取引とは分けて考えられます。
| 項目 | NISAの特徴 |
|---|---|
| 税制 | 配当や売却益が非課税 |
| 取引形態 | 現金取引のみ レバレッジや信用取引は対象外 |
| 責任範囲 | 投資家の出資額が上限 追加請求は原則ない |
証券取引ルールの範囲
証券会社は口座種類に応じた取引ルールを適用します。
現物取引口座では購入資金の範囲内で取引が行われるため決済不能が生じないよう管理されます。
信用取引や先物などの証拠金取引では追証や追加支払いが発生することがありますが積立NISAはこれらに該当しません。
万が一のシステムエラーや不正取引があった場合は各証券会社の補償や対応ルールに基づいて処理されます。
追加支払いが発生するケースの限定
積立NISAで通常の購入を行っている限り元本割れは自己の損失であり借金にはなりません。
ただし例外的に追加支払いが生じ得るケースがあります。
- 信用取引での追証
- 先物やFXなどの差損が確定した場合
- 口座の不正利用による損害発生
- 取引ルール違反に伴う清算費用
これらのケースはいずれも積立NISAの現物投資そのものではなく別の取引形態や特殊な事案に起因します。
結論として積立NISAで元本割れが起きても通常は借金にならない点を理解しておくことが大切です。
積立NISAの元本割れ時に取るべき具体的対応

積立NISAで元本割れが起きたときは感情的な判断を避けて冷静に対応方針を決めることが重要です。
ここからは現実的に検討できる具体的な対応を項目ごとに示します。
保有継続判断
長期の投資期間が残っている場合は保有継続が有力な選択肢です。
積立投資は時間を味方にすることで平均取得単価を下げる効果が期待できます。
投資対象のファンドやETFの運用方針や手数料に問題がないか確認してください。
積立NISAの非課税メリットを考慮すると短期の動揺だけで売却するのは必ずしも最善ではありません。
ただし生活費が逼迫している場合や借金リスクがある場合は保有継続を見直す必要があります。
部分売却判断
全てを一度に売るのではなく部分売却でリスク調整する方法があります。
部分売却を検討する主な理由は次のとおりです。
- 生活資金の確保
- ポートフォリオのリバランス
- 特定ファンドの長期的な不安
- 借金返済のための緊急資金確保
売却する際は必要最低限の金額に抑え将来の回復機会を残すことを意識してください。
短期的な相場変動で損切りを繰り返すと回復の恩恵を受けにくくなります。
積立額見直し
家計状況や収入の変化に応じて積立額を一時的に減らす選択は合理的です。
積立を続ける余裕がなければ無理に継続せず生活を優先してください。
借金をしてまで積立を維持するのは避けるべきです。
余裕資金が戻った段階で積立額を再設定する計画を立てておくと安心です。
資産配分の見直し
元本割れを契機にリスク許容度に合った配分へ調整するのも有効です。
| リスク許容度 | 検討する配分例 |
|---|---|
| 高い | 株式比率高め 債券比率低め |
| 中間 | 株式債券のバランス型 |
| 低い | 債券重視 現金比率を確保 |
資産配分は年齢や目標時期に合わせて変更することが原則です。
リスクを下げるために現金や債券の比率を上げると元本変動は抑えられます。
専門家相談
将来の不安や借金が絡む場合は専門家に相談するのが安心です。
公的な相談窓口や認定ファイナンシャルプランナーへの相談を検討してください。
借金が既にある場合は債務整理や返済計画の専門窓口にも相談すると選択肢が広がります。
相談時は保有資産の内訳と生活収支を整理してから臨むと有益な助言が得られます。
積立NISAの元本割れを避ける運用戦略

積立NISAで元本割れのリスクを抑えるための基本的な考え方を分かりやすくまとめます。
借金をして投資を行うことの危険性も併せて触れます。
長期積立の効果
時間を味方につけることで短期的な価格変動の影響を和らげられます。
ドルコスト平均法により購入時期による価格変動が平準化されます。
複利効果は投資期間が長いほど有利に働きます。
歴史的に見れば株式は長期で上昇しやすい傾向がある一方で短期の下落は避けられません。
借金をして積立額を増やすと下落局面で返済負担が重くなり元本割れが借金問題に発展する恐れがあります。
分散投資
一つの資産や地域に偏らないことで特定のショックに対する耐性が高まります。
- 国内株式と海外株式の組合せ
- 株式型と債券型の併用
- 先進国と新興国のバランス
- 複数の業種に分散
投資先を分散しても市場全体が下落する場合は損失が避けられない点には注意が必要です。
低コストファンド選び
運用コストは長期のパフォーマンスに直接影響します。
信託報酬や隠れたコストを抑えると複利効果を最大限に活かせます。
| 指標 | 目安 | 注目ポイント |
|---|---|---|
| 信託報酬 | 低水準 | 長期負担を軽くする |
| 運用資産総額 | 十分な規模 | 継続性の目安 |
| トラッキング誤差 | 小さいこと | ベンチマークへの追従性 |
インデックスファンドは低コストの選択肢として有力です。
定期的なリバランス
目標資産配分から大きく乖離した場合に元の比率に戻す操作がリバランスです。
リバランスを行うことでリスク水準を維持できます。
リバランスの頻度は年1回や半年ごとなどライフスタイルに合わせて決めると続けやすいです。
売買に伴うコストや税金を意識して実行タイミングを選んでください。
積立頻度の最適化
月1回の積立が手間とコストのバランスで一般的には使いやすいです。
より細かく積み立てると価格変動をさらに平準化できますが手数料負担が増える場合があります。
まとまった資金がある場合は一部を一括で投じて残りを積立に回すハイブリッドも選択肢です。
重要なのは生活資金と緊急予備を確保したうえで余裕資金で積み立てることです。
借金で積立を行うことは推奨できません。借金が残る状態での投資は元本割れが借金問題に直結するリスクを高めます。
積立NISAの元本割れで損失を最小化する税務上の注意点
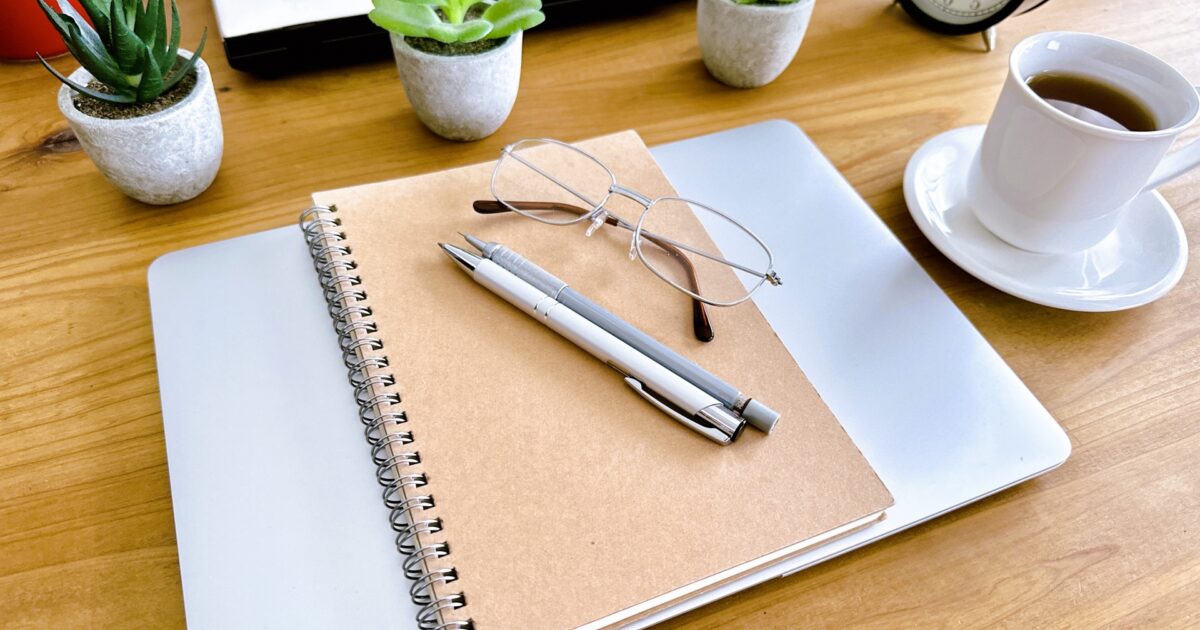
積立NISAは投資の元本が減ることがあり得る制度です。
税制優遇がある一方で損失に関する取り扱いは一般の課税口座と異なります。
税務上の損失計上不可
積立NISA口座で生じた損失は税務上の損失として計上できません。
売却して確定した損失も所得税や住民税の計算上は反映されないため税金が還付されることはありません。
積立NISA 元本割れ 借金の懸念がある場合は、損失が税務上の控除につながらない点を押さえておく必要があります。
投資資金を借入で賄っている場合は元本割れが返済負担に直結する点に注意してください。
他口座との損益通算不可
積立NISA口座の損失は他の課税口座の利益と損益通算できません。
課税口座で発生した譲渡損益の通算や繰越控除の対象外になります。
| 項目 | 累計の取り扱い |
|---|---|
| NISA口座の損失 | 対象外 |
| 課税口座の損益 | 通算可能 |
| 繰越控除 | 適用不可 |
課税口座とNISA口座は税務上で明確に区別される点を理解しておくと実務で混乱しません。
確定申告の注意点
積立NISAの損失そのものを確定申告で申告して控除することはできません。
- NISA口座分は申告不要で税金は非課税扱い
- 課税口座の損失は申告して損益通算や繰越控除が可能
- 借入で投資した場合の利息控除は原則厳格
借金をして投資した場合は税務と返済の両面を分けて考えることをおすすめします。
不明点や大きな金額が絡む場合は税理士など専門家に相談して具体的な対応を確認してください。
積立NISAの元本割れに関するよくある誤解

積立NISAの元本割れは投資のリスクを正しく理解していないと誤解されやすいです。
ここでは典型的な間違いを取り上げて整理します。
誤解を解くことで冷静な判断がしやすくなります。
借金になるという誤解
積立NISAで運用している資産が評価損になることはあり得ますが借金が発生するわけではありません。
積立NISAは購入時に現金で投資信託やETFを買う仕組みでありマイナス残高になる仕組みではありません。
信用取引やレバレッジを使った取引なら借金や追証が発生するリスクがありますが積立NISAではそれらは利用できません。
例外的に別の取引でマイナス残高が生じた場合は借金扱いになる可能性がありますが積立NISA自体が原因で借金になることは基本的にありません。
元本保証の誤認
元本保証があると思い込む人がいますが積立NISAは元本保証の商品ではありません。
- 元本は必ず守られる
- 元本割れはあり得ない
- 短期で必ず利益が出る
これらは誤ったイメージであり投資信託の価格は市場で決まるため元本割れは起こり得ます。
積立NISAの主なメリットは運用益が非課税になる点であり元本保証とは別の特徴です。
短期下落の過大評価
短期間の価格下落を過大に評価してすぐに判断を誤る人は少なくありません。
| 期間 | 市場の特徴 |
|---|---|
| 短期 | 価格変動が大きい |
| 中期 | 変動は残るが傾向が見える |
| 長期 | リターンが安定しやすい |
過去の実績を見ると短期の下落は頻繁に起こる一方で長期保有で回復するケースが多いです。
積立投資は時間を分散することで購入単価を平準化する効果が期待できます。
暴落で即売却すべきという誤解
暴落直後に慌てて売却すると評価損を確定させることになります。
長期投資の前提がある場合は市場が落ち着くまで保有を続ける選択肢もあります。
資金需要などでどうしても売却が必要な場合は目的と時間軸を再確認してから判断してください。
感情的な売買を避けるために投資方針を事前に決めておくことが有効です。
元本割れと借金リスクを踏まえた積立NISAでの行動方針

投資は余裕資金で行い借金をして積立を続けないことを最優先にしてください。
積立NISAは長期投資が前提なので短期的な元本割れで慌てて解約しない判断も重要です。
生活防衛資金として生活費の3〜6か月分を確保してから積立を始めてください。
リスク許容度に応じて株式比率を下げる、バランス型を選ぶなど資産配分を調整してください。
運用状況は年に1回程度見直し、目標やライフプランに合わなくなったら積立額や商品を変更しましょう。
最終的には借入での投資は避け、負債がある場合は返済を優先する方針を基本にしてください。

